どんなニュースもCGにしてしまう、あの台湾のテレビ局NMAが、尖閣諸島問題をCG化してました。パンダと忍者の戦い。
タグ: 日本
「海角七号」 – 台湾映画史上最大のヒットは「日本超好き好き」映画だった
映画「海角七号」、今日本でもやってるのですが、「こういう人にはオススメ」というのがあるんでちょっと書いてみたいと思います。
台湾滞在中に、新しめのガイドブックや台湾旅行ブログなどでプッシュされていて気づいた「海角七号」という映画があります。一年遅れで今ちょうど日本各地で上映中なんですが、台北のレンタルショップでDVDを借りて英語字幕で見てみました。
楽しく、笑える映画でもある
日本語のサイトを見ると感動系の映画みたいで、実際に感動もするのですけど、コメディとしても楽しいところがたくさんあります。
なんか、単館系の映画やハリウッド以外の映画って、日本に来たときに中身と関係なく「泣けるラブストーリー・感動作」みたいなポスターや宣伝になることって多いですが、実際コメディ成分の方が多いかなーと思います。
# そういえば「マンマミーア」の時も同じことを思ったっけ。すごく楽しい映画なんですが、スイーツ(笑)系の宣伝がテレビとかでガンガン流されていたようで、他にも見て楽しそうな層はあったのになあ、と。
日本だらけ
この映画は台湾製で完全台湾人向けに作られているにもかかわらず、「日本」が多数出てきます。田中千絵(トニー・タナカの娘)とかの日本人俳優も出てますし、ナレーションは日本語だし、台湾人俳優も日本語をしゃべったりと、半分ぐらい日本語でやってるんじゃないか、というぐらい。
そして、そこで出てくる「日本」が、いいイメージの日本ばかりなんですね。台北の街中をちょっと歩くだけで、「ファミリーマート」とか「セブンイレブン」とか「三越」とか「そごう」とか、その他たくさんの日本ブランドに出会うので、日本が好きな人が多いのはわかったのですけれど、それにしても日本や日本人の扱いがとても良い映画。
似た映画でいうなら「ラスト・サムライ」でしょうか。いや、僕はラスト・サムライ見てないんで、間違ってるかもしれませんが、見た人の感想を聞いた感じでは似てるかと。日本人としてこそばゆい思いをするかもしれません。「そこは日本語にしなくていいだろう」というところ(ある歌とか)まで日本語が押し出されてたりします。
実はこういう映画と近い(、と思う)
それから、バンド・チームものとしては、「フラガール」とか「ブラス」とか「フルモンティ」とかとの共通点も多いと思いました。いろいろとうまくいかないバラバラなチームが、苦労を乗り越えて最後には、というやつ。上記の映画が好きな人は、普通にそういう映画としてだけでも楽しめるのではと思いました。
僕はこのへんのチームものが、「がんばれベアーズ」とか「マイティダックス」とか「メジャーリーグ」とかのスポーツ物も含めて大好きなので、ツボにはまったところはあります。
台湾で大ヒット、の背景
この海角七號、台湾では2008年に公開されて、洋画を含めてもタイタニックに次いで史上2位、国内映画としては興行成績史上1位を取っています。
台湾ではかなり多くの人が見ているし、見てない人でも社会現象となったことから映画の存在はまず知っているようです。滞在中にいろいろな人との雑談で「この映画を見た」と言ったら、かなり盛り上がりました。必ず「で、どう思った?」と訊かれるのですが、だいたいは「とても面白かったんで繰り返し見ちゃったよ。けど君ら日本好き過ぎだなあ」という感じで答えてました。
日本版の予告編は公式サイトで見られるので、ここではオリジナルの予告編を。ここでも、いきなり日本語から映画がはじまっています。
しいて欠点を挙げるとするなら、元々台湾人向けに、台湾人が面白いと思うように作られただけあって、日本語がわかる人が見るとき向けのチェックが足りないところでしょう。
たとえば、台湾人だけど日本語が話せる、という設定の登場人物が二人いるのですが、彼らの日本語はかなり棒読みで不自然です。台湾人が見てるときは中国語の字幕が出ているので「ああ、こういうことを日本語でしゃべってるんだな」で済むのですけど、日本人が聞くとひっかかるかも。
老人役の人(コメディパートを支えるとても面白いキャラクターですが)は、設定が80歳の戦前生まれで日本語もわかる、ということなのですが実際には60歳だそうで、そのあたりしょうがないところもあるのですけど。あと日本人歌手の中孝介さんは、ナレーションはうまいのですが演技が本職でないだけにちょっと…
これらについては、「外国映画ががんばって日本語をいろいろ使ってくれている」という気持ちでスルーしてあげてください。
他にも、バンドメンバーのそれぞれが、客家だったり原住民出身だったりと、様々な人種や言語が混ざっている台湾を良く表している、ということです。残念ながら言葉や習慣の微妙な違いがわからないので、台湾人ほど大うけできない箇所もあるかもしれませんが。
また、この映画があまりに日本びいきなので、中国本土では上映禁止になったりしたそうです。中国と台湾、そして日本との関係から、映画本体が面白いかどうかとは別にこの映画をほめたり、けなしたり、という動きもいろいろあるようで、そのあたりは外野が嫌な感じです。
本作の監督は、別の「本当に作りたい映画」を撮るための資金稼ぎとしてこの海角七号を作ったそうで、その本当に作りたい映画(今作ってるらしいです。主演がなんとあのビビアン・スー)は、戦前に日本人と台湾原住民が殺し合いをした霧社事件を扱ったものだそうです。ですから、海角七号も、何も日本のためや政治的な意図で作った映画ではなく、今の台湾人に受けるようにはそういう味付けが効くと思って作ったのではないかなと感じました。
僕はDVDを借りている間に、3度も通しで見たぐらいで、もちろんこの映画は大好きになりました。見ても損はしない映画かなと思います。日本ではそんなにたくさんの映画館ではやってないし、もう上映が終わった地方もありますが、後日DVDででも。
[追記 2010-07-07] 日本語版のDVDも出てますね。日本語吹き替えも入ってるらしいので、吹き替えで見れば変な日本語の問題はなくなりそうです。もちろん、オリジナル音声も欠点はあるもののとても味があると思いますけど。
日本と西欧の住所システムの違いをわかりやすく解説した動画
Derek Siversさん(@sivers)が公開した動画がコメント欄で盛り上がっているようです。
動画では、アメリカ等では通りに名前があるのに、日本では地域に名前があり、ほとんどの道には名前がないことを、地図を使ったアニメーションでわかりやすく説明しています。
ほかに、患者が病気になったときにお金を取る西洋の医師と、患者が健康な間にお金を取る中国の医師、アフリカでのリズムの取り方の違い、世界地図の上はどっちか、など、地域によって考え方が違う例を紹介しています。
Delphi for PHP作者の来日記まとめ
先月の第40回PHP勉強会@関東は、スペインからDelphi for PHPの作者Jose Leonさんを迎えてのスペシャルだったわけですが、Joseさんの日本滞在の感想等が彼のブログで上がっていたのでご紹介しておきます。
Delphi for PHP » Developer Summit 2009 – Japan
デブサミ初日の感想。参加者の多さと熱心さに感心されているようです
Delphi for PHP » Developer Summit 2009 – Japan (II)
デブサミ二日目。彼自身のセッションがあったことの報告です。そのあと、各メディアとのインタビューに臨んだようです。
PHP勉強会とそれに続く泊まりでのハッカソンの感想。勉強会で発表されたOpenPear等にも言及されてます。
Delphi for PHP » Developer Camp 2009 and Open Source Conference at Japans Electronics College
オープンソースカンファレンス(OSC)の感想。写真が「日本」ですね。カメラ量販店の技術書棚も印象に残った様子。
Matzことまつもとゆきひろさんとのツーショット写真も。Delphi for Rubyの可能性について話したとか。
最後は、取材を受けて日本で記事になったページをそれぞれ紹介しています。
「ニッポン社会」入門―英国人記者の抱腹レポート
イギリスの新聞「デイリー・テレグラフ」東京特派員として日本のニュースをイギリスに伝える、日本通イングランド人コリン・ジョイスさんの日本紹介本を読みました。たぶんたつをさんのところで見つけたもの。
[am]4140882034[/am]
英語の原本が出版されているわけではないので(原稿は英語で書かれて、日本人が翻訳しています)、日本紹介、という形をとりつつも、イギリス人向けに書いたというよりは日本人向けに書かれた本です。
イギリス風かどうかわからないが、著者のユーモアあふれる語り口にはつい頬が緩んでしまします。
「電車の床にかばんを置いてはいけない。込んでくると、身を屈めることができなくなり、かばんを取れなくなってしまう」
「歌舞伎は歌舞伎町でやっていない」
東京に十四年住んでいることと、日本語を学んだり街中の人たちに話しかけていったりという著者の積極的な姿勢もあってか、日本や日本人、日本の生活や文化に関する観察や感想は読んでいてとても楽しいです。
何をどのように変わってると思うか、というのを読むことで、日本では当たり前だけどイギリスや西洋一般では違う、ということをたくさん学ぶことができますね。著者の日本語学習経験から、外国語を学ぶとはどういうことか、という気づきも多いです。
『しかし、日本人読者のみなさん、これだけはどうか誤解しないでいただきたい。日本語学習者はどこかでその擬声語ないし擬態語をきちんと学ばないかぎり、その意味を理解できない。音から自然と意味を推測することなどできはしないのだ。「おなか、空いてる?」は理解できても、「おなか、ペコペコ?」はわからないかもしれない。』
イギリスの料理については一章を割いて擁護がされていますが、僕はイギリスに住んでたときにイギリスの料理を(カレー、中華、ケバブももちろんですが本来のイギリス料理も)たいへん堪能し、楽しんでいたので、ここは同感です。もっとも、他のヨーロッパ人の同僚や友人達からは「おまえの舌はおかしい」と言われましたが。
拾三章の「イギリスに持ち帰るべきお土産」も面白い。そもそもイギリスやアメリカに誰かを訪ねるとしても、お土産を持っていく必要はないのだけれど、友人に何かを持っていくとしたら、日本のどんなものが変わっていたり、喜ばれたりするのか、ということを面白く列挙しています。
拾四章「イギリス人が読みたがる日本のニュース」では、自分が紹介したい日本が、いかにイギリスの新聞向けには通らないか、という悩みも語られています。イギリスの読者は、そもそも日本のニュースに対しては興味が薄いし、少ない記事の中で読者を面白がらせようとすると、どうしてもウケを狙った、日本の実態ともいえないニュースを書かされたり、提出した原稿をどんどん変更されてしまったりする、ということです。
これは一時期問題になった、毎日新聞英語版の事件にも通じますし、逆に、日本の新聞に変わった海外のニュースが載っていても、それは現地の人でも知らなかったり、現地でもおかしいとされていたりということもあるでしょう。言葉や文化を越えて何かを照会するときに常につきまとう問題だと思います。
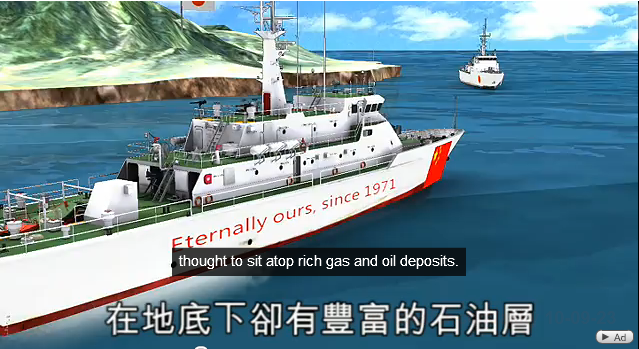
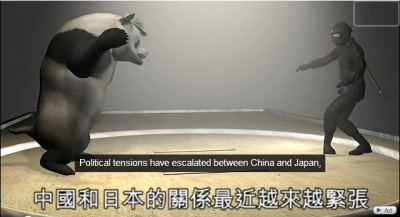

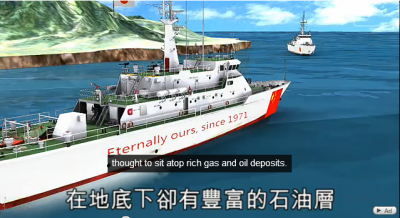
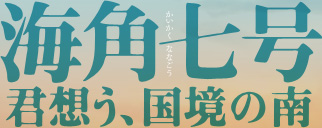

![海角七号/君想う、国境の南 [DVD]](http://images.amazon.com/images/P/B003II8B98.01._PC_SCMZZZZZZZ_.jpg)